はじめに
軍争篇は、『孫子』の第7篇でありながら、行軍や補給線、先手必勝に関する実務的な知見が詰まった章です。計篇~勢篇・虚実篇までの諸概念(戦略的準備、不敗の態勢、攻撃の勢、敵の誘導)を、実際の移動と地形の観点で応用する形になっています。
前回【軍争篇(2)】では、「先に要衝を押さえる」「危険なルートは避ける」など、より具体的な行軍法を学びました。本稿【軍争篇(3)】では、軍争篇全体をまとめ直し、次章「九変(きゅうへん)篇」へとつなげます。
軍争篇の要点
(1) 先手必勝――佚と勞
- 「先に戦場を占拠する側は楽(佚)、後から来る側は苦(勞)」
孫子兵法の根幹である“先手を取って相手を分散させ、自軍は集中する”方針が、軍争篇で明確に地形・行軍の話へ落とし込まれています。 - 形篇や勢篇の考えを応用し、主導権を握って動く側が圧倒的に有利になる仕組みを説明。
(2) 行軍のスピードと補給
- 短期決戦を望む作戦篇とも連動し、行軍や補給ルートの選択がどれほど重要かを強調
- 行軍が遅く、補給が途切れれば兵士の士気は下がり、“勞”ばかりが増す → 自軍が佚に保つためには素早い移動と的確なルート選択が不可欠
(3) 地形と避けるべき場所
- 軍争篇後半では、「深いところや険しい道、孤立した峰」を避けるなど、地形リスクを具体的に指摘
- あくまで「勝てる場所だけを選び、無理なところを攻めるのは避ける」という孫子の合理性が通底
(4) “利で誘い、害で遠ざける”再び
- 虚実篇で学んだ誘導術が、軍争篇でも繰り返される
- 行軍中に“魅力的な標的(利)”を匂わせて敵をそちらに引っ張り、自軍は別ルートで要所を押さえる、など
- こうして敵を翻弄し、自軍は楽に移動して先手を取れる
形・勢・虚実×軍争――四つの柱
- 形篇: 不敗の態勢(守備・基盤)
- 勢篇: 攻撃の爆発力(短期集中)
- 虚実篇: 敵の誘導・弱点を突く
- 軍争篇: 実際の行軍・地形把握・先手確保
この4つが揃うことで、孫子の言う“戦わずして勝つ”道筋がさらにリアリティを帯びます。ただ頭脳戦や兵力に頼るだけでなく、実際の地形移動やスピード管理がきちんと計算されるからこそ、消耗を最小化して勝利を収められるわけです。
現代への応用
(1) スピード優先のビジネス戦略
- 軍争篇の先手思想をビジネスに当てはめれば、「新市場への早期参入」「特許・ライセンスの先取り」「SNSや広告枠の先行確保」などが挙げられる
- 後から参入する企業は“勞”に苦しむ → 追い上げるのに時間とコストがかかり、不利な構造を強いられる
(2) プロジェクトでのリード
- 早めに環境やリソースを整え(不敗の形)、主要ステークホルダーを押さえる → 競合プロジェクトは追随が難しくなる
- “危険な道”や“不確実な要素”に手を出さない → リスクが高い領域を相手に委ね、様子を見ながら確実な成果を積み重ねる
(3) 大規模イベントやキャンペーン
- 先に会場や主要プラットフォームを確保 → 競合が後からスケジュールを組もうとすると難しくなる
- 迅速な準備と周到な“補給”計画 → 予算やリソースを先行で抑え、後発組を追いつけない状況にする
軍争篇を超えて――次章「九変篇(きゅうへん)」へ
(1) 行軍・地形論はまだ続く
軍争篇は先手必勝と基本的な行軍要領を提示しましたが、次の「九変篇」や「行軍篇・地形篇」で、さらに地形に応じた戦い方、軍の動かし方が細分化されます。
(2) 九変篇とのつながり
- 九変篇は、地形や状況が刻々と変化する中で、将軍がどう判断して行動パターンを変化させるかを扱う
- 軍争篇の「先手を取る」という基本戦略が、九変篇では多様な地形・情勢の変化に適応させる形で発展していく
(3) 孫子兵法の流れ
計篇(戦略)→ 作戦篇(補給)→ 謀攻篇(戦わずして勝つ)→ 形篇(不敗の形)→ 勢篇(攻めの勢)→ 虚実篇(誘導術)→ 軍争篇(行軍と先手) → 九変篇(地形・状況多変化対応)…
ここまで進むと、孫子兵法がいかに複合的・総合的な理論かが一段と明瞭になるはずです。
5. まとめ
【軍争篇(3)】として、軍争篇全体を総括しました。
- 先に戦場を占拠する者は楽、後から来る者は苦
- 危険な地形を避けつつ、要衝を迅速に確保
- 行軍の補給を整え、自軍に“佚”を保ち、相手には“勞”を押し付ける
- 形・勢・虚実で築いた基盤を、移動と地形の観点で具体化
軍争篇を通じて、孫子兵法が“戦前分析→隊形と勢→誘導→行軍・補給”と、段階的に戦術を積み上げていることがわかります。次回【第30回】からは、第8篇「九変篇」に入り、さらに地形や状況変化に合わせて柔軟に方針転換する考え方を学びましょう。ここに至って“形・勢・虚実・軍争”の知恵がまた新たな次元で活かされるはずです。
あとがき
- 軍争篇の意義
計篇や謀攻篇が戦術レベルの詭道を示す一方、軍争篇は実務的な行軍計画と先手確保を説く。補給とスピード、地形の選択がいかに大切か、改めて思い知らされます。 - 現代での展開
軍争篇の概念は、ビジネスや政治において「先手を打ち、市場や交渉を掌握する」テクニックに直結。単なるリスク回避でなく、“要所への集中”と“相手を分散させる”の応用法がいたるところで見られます。 - 九変篇への展開
次章は、地形や状況によって戦略を多様に変える「九変篇」。軍争篇が示す基本ルールを、実際の変化にどう即応させるか――そこに孫子兵法のさらなる奥深さが現れます。


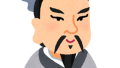
コメント